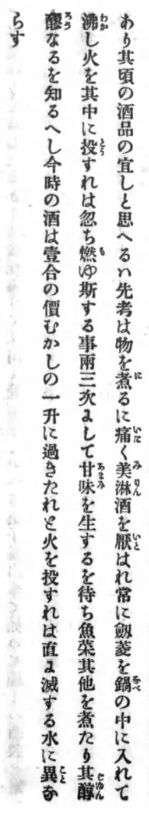”「ザ・シチュー(シチューとしか呼びようのない料理)」”
”本当においしいのでこれ以外のもの一切入れちゃだめ!”
あーこのシチュー食べたことありますわ、三十数年前の新世界で。
”本当においしいのでこれ以外のもの一切入れちゃだめ!”
あーこのシチュー食べたことありますわ、三十数年前の新世界で。
https://twitter.com/inadashunsuke/status/1384476588159373312
三十数年前の新世界は、観光客も女性客もいない「変なクリーチャーが蠢くスター・ウォーズの酒場」みたいなところでしたが、それだけに印象が強かったです。
そこで食べたのが、この水だけで作ったようなシチューうどんと串かつでした。
そこで食べたのが、この水だけで作ったようなシチューうどんと串かつでした。
この水だけシチューうどん、ひょっとしたら明治時代のシチューの名残なのかもしれません。
明治30年代から屋台の洋食屋が夜の街に現れるようになります。そこでのシチューは、水だけでつくったものでした。
なにせ値段が三銭という極安シチューでしたので、材料費がかけられない。
明治30年代から屋台の洋食屋が夜の街に現れるようになります。そこでのシチューは、水だけでつくったものでした。
なにせ値段が三銭という極安シチューでしたので、材料費がかけられない。

”スープを用いずつゆのみ多く”というのは、出汁を取っていないという意味。
本来英語では出汁のことをbrothというのですが、明治時代の洋食のレシピ本においては、brothではなくソップ(スープ)という和製英語を使いました。
このソップで「シチウソウス」を作りシチューのベースとします。
本来英語では出汁のことをbrothというのですが、明治時代の洋食のレシピ本においては、brothではなくソップ(スープ)という和製英語を使いました。
このソップで「シチウソウス」を作りシチューのベースとします。

しかしながら、安いことが目玉だった洋食屋台のシチューには、そんな手間と金はかけられません。
明治43年の『無資本実行の最新実業成功法』には、洋食屋台のシチューレシピが載っています。
やはり出汁はとっていないようです。バターは入れていますが。
明治43年の『無資本実行の最新実業成功法』には、洋食屋台のシチューレシピが載っています。
やはり出汁はとっていないようです。バターは入れていますが。

洋食屋台では、この水だけシチューをご飯にかけた「シチウ飯」というのも売っていました。よく売れていたそうです。
シチューにご飯はありかなしか論争がありますが、少なくともシチューで飯を食べる習慣は明治時代からあったのです。
シチューにご飯はありかなしか論争がありますが、少なくともシチューで飯を食べる習慣は明治時代からあったのです。

この『無資本実行の最新実業成功法』は大阪で発行された本。
ひょっとしたらシチューうどんの祖先はシチウ飯だったのかも……
ひょっとしたらシチューうどんの祖先はシチウ飯だったのかも……
ここで宣伝です。
新刊『串かつの戦前史』においては、この洋食屋台がいかに隆盛し、そして衰退していったか、その歴史を追っていきます。
bit.ly/2ScuEuJ
なぜなら、この洋食屋台が串かつが生まれる母体となったと考えるからです。
新刊『串かつの戦前史』においては、この洋食屋台がいかに隆盛し、そして衰退していったか、その歴史を追っていきます。
bit.ly/2ScuEuJ
なぜなら、この洋食屋台が串かつが生まれる母体となったと考えるからです。
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh