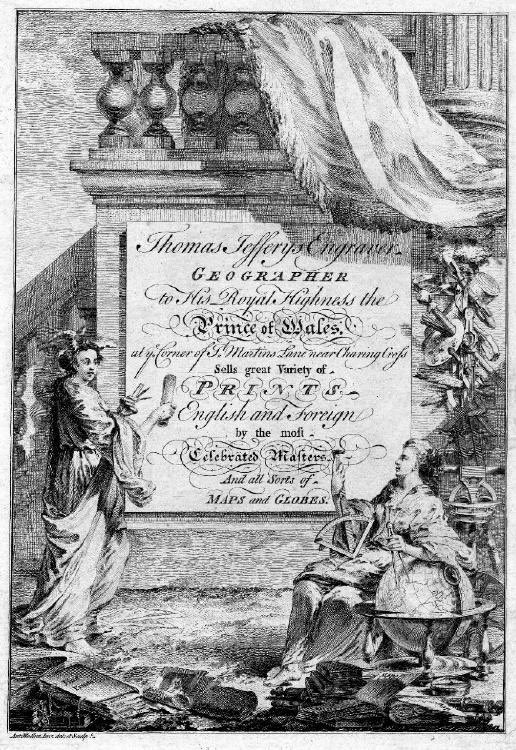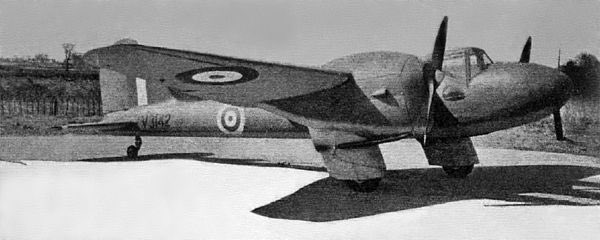まぁ、そうなるよねーw
文字通りの『役者が違う』ってやつね。
ま、あからさまに怯えてやらんだけ、マシ。
ま、あからさまに怯えてやらんだけ、マシ。
信長によらず、大名がたは甘党が多かったとか?
おお、光秀きた。
甘味、って本当にこの時代めちゃくちゃ重たい価値を持ってたのね……
家臣が次々と問題起こしそうだぞ。
お上りさん軍団。
お上りさん軍団。
信長の一銭斬り……
日本史は疎いけど、最新の歴史観に近い描写だよね?
信長は当初、室町幕府体制における筆頭者を目指してた。
信長は当初、室町幕府体制における筆頭者を目指してた。
いい描写だなぁ。お市様の器量が見える。
ううう、この義昭は嫌だなぁ……
義昭優秀が最近の主流なのに。
義昭優秀が最近の主流なのに。
あああ、金平糖をそんな。
毎回毎回、格上に振り回される家康……
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh

 Read on Twitter
Read on Twitter