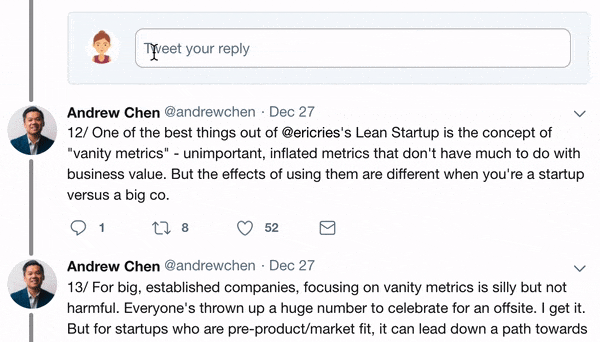以前の考察から
亜鉛+EGCG(亜鉛イオノフォア)には
感染予防〜後遺症まで幅広く期待
▶︎細胞侵入前のS蛋白に結合
→感染予防
▶︎細胞内に亜鉛を運んでウイルスRdRpを阻害
→重症化予防
▶︎脳内の残存ウイルスを駆逐
▶︎細胞の線維化を抑制
▶︎嗅覚上皮細胞の再生促進
▶︎自己免疫疾患の緩和
亜鉛+EGCG(亜鉛イオノフォア)には
感染予防〜後遺症まで幅広く期待
▶︎細胞侵入前のS蛋白に結合
→感染予防
▶︎細胞内に亜鉛を運んでウイルスRdRpを阻害
→重症化予防
▶︎脳内の残存ウイルスを駆逐
▶︎細胞の線維化を抑制
▶︎嗅覚上皮細胞の再生促進
▶︎自己免疫疾患の緩和
ちなみに
「以前の考察」の一部は
こちらのスレッドを意味します。
※考察の一部分
後遺症状を大きく4分類して考察しました。
①免疫特権部位へのウイルス残留
②細胞の瘢痕組織化
③自己免疫疾患
④嗅覚障害
かなりの長文スレッドですが、
ご興味ある方はご覧ください。
「以前の考察」の一部は
こちらのスレッドを意味します。
※考察の一部分
後遺症状を大きく4分類して考察しました。
①免疫特権部位へのウイルス残留
②細胞の瘢痕組織化
③自己免疫疾患
④嗅覚障害
かなりの長文スレッドですが、
ご興味ある方はご覧ください。
https://twitter.com/rikanojikan/status/1369233660826710019?s=21
亜鉛イオノフォア成分として
学術論文によく名前があがる植物成分
・EGCG
・ケルセチン
・ルテオリン
・レスベラトロール
・ルチン
それぞれ、
どのような植物成分なのか見ていきます。
学術論文によく名前があがる植物成分
・EGCG
・ケルセチン
・ルテオリン
・レスベラトロール
・ルチン
それぞれ、
どのような植物成分なのか見ていきます。
▶︎EGCG
エピガロカテキンガレート
チャノキの葉に含まれるカテキンの一種。
緑茶カテキンは大きく8種類あり、
そのうちの分子構造的に
ガレート基がつく4種のひとつ。
学術的に確認済の植物成分としては
最大値の亜鉛イオノフォア作用が確認されている。
同じチャノキ葉でも紅茶には含まれない。
エピガロカテキンガレート
チャノキの葉に含まれるカテキンの一種。
緑茶カテキンは大きく8種類あり、
そのうちの分子構造的に
ガレート基がつく4種のひとつ。
学術的に確認済の植物成分としては
最大値の亜鉛イオノフォア作用が確認されている。
同じチャノキ葉でも紅茶には含まれない。
なぜ紅茶にはEGCGがない?
▶︎茶葉の発酵度合いが違うから
緑茶も紅茶も元は同じ茶葉。
その葉を完全発酵させたものが紅茶。
発酵させていないのが緑茶。
この工程によってEGCG量は変わるが、
もちろん茶葉の日照時間や
抽出温度によっても変化するため
どの緑茶にも豊富に含まれるわけではない。
▶︎茶葉の発酵度合いが違うから
緑茶も紅茶も元は同じ茶葉。
その葉を完全発酵させたものが紅茶。
発酵させていないのが緑茶。
この工程によってEGCG量は変わるが、
もちろん茶葉の日照時間や
抽出温度によっても変化するため
どの緑茶にも豊富に含まれるわけではない。
緑茶から摂る場合、
EGCGは80℃以上のお湯で
最も多く抽出されやすい一方、
抽出後は82℃以上で構造変化をします。
つまり、
最大限にEGCGを抽出できて
なおかつEGCGを壊さなくてすむ
最適な抽出温度は80~81℃で、
抽出後の保管温度は82℃未満です。
EGCGは80℃以上のお湯で
最も多く抽出されやすい一方、
抽出後は82℃以上で構造変化をします。
つまり、
最大限にEGCGを抽出できて
なおかつEGCGを壊さなくてすむ
最適な抽出温度は80~81℃で、
抽出後の保管温度は82℃未満です。
▼EGCG
亜鉛イオノフォア以外の作用
▶︎コロナウイルス直接阻害
→植物成分では最大値(Era University)
▶︎コロナ後遺症の要因
自己免疫疾患細胞Th17をつくらせない
(IL-6・STAT3を阻害)
▶︎細胞線維化因子TGF-βの抑制
▶︎強力な殺菌・食中毒予防作用
▶︎抗がん作用
researchsquare.com/article/rs-195…
亜鉛イオノフォア以外の作用
▶︎コロナウイルス直接阻害
→植物成分では最大値(Era University)
▶︎コロナ後遺症の要因
自己免疫疾患細胞Th17をつくらせない
(IL-6・STAT3を阻害)
▶︎細胞線維化因子TGF-βの抑制
▶︎強力な殺菌・食中毒予防作用
▶︎抗がん作用
researchsquare.com/article/rs-195…
▶︎ケルセチン
亜鉛イオノフォア作用はEGCGの約半分
タマネギに多く含まれるとされるが、
実は白い本体部分にはほとんどなく、
日照によって変色した茶色の外皮に多く含まれる。
特にマメ科エンジュの蕾に多く含まれ、
その他にはリンゴやブロッコリー、
モロヘイヤにも比較的多く含まれる。
亜鉛イオノフォア作用はEGCGの約半分
タマネギに多く含まれるとされるが、
実は白い本体部分にはほとんどなく、
日照によって変色した茶色の外皮に多く含まれる。
特にマメ科エンジュの蕾に多く含まれ、
その他にはリンゴやブロッコリー、
モロヘイヤにも比較的多く含まれる。
タマネギは値段も安いし身近な野菜。
タマネギから摂りたい場合は、
皮を剥いで白い本体部分をぶつ切り。
日当たりのよい場所で
新聞紙などの上に手でばらし並べて
4〜5日間、よく日光にあてると
ケルセチンが多量に生成されます。
まんべんなく日があたるよう
こまめにかき混ぜると良いです。
タマネギから摂りたい場合は、
皮を剥いで白い本体部分をぶつ切り。
日当たりのよい場所で
新聞紙などの上に手でばらし並べて
4〜5日間、よく日光にあてると
ケルセチンが多量に生成されます。
まんべんなく日があたるよう
こまめにかき混ぜると良いです。
ケルセチンの亜鉛イオノフォア力は
EGCGの半分程度に落ちるが、
脳への到達率
(血液脳関門BBB透過)が高く、
新型コロナへの直接阻害力も
EGCGほど高くはないが、比較的高い。
<S蛋白阻害力 / 脳到達レベル>
▶︎ EGCG:8.66 / 4%
▶︎ QCT:6.59 / 65.54%
脳への到達に至っては
EGCGの約16倍だ。
EGCGの半分程度に落ちるが、
脳への到達率
(血液脳関門BBB透過)が高く、
新型コロナへの直接阻害力も
EGCGほど高くはないが、比較的高い。
<S蛋白阻害力 / 脳到達レベル>
▶︎ EGCG:8.66 / 4%
▶︎ QCT:6.59 / 65.54%
脳への到達に至っては
EGCGの約16倍だ。
【ケルセチンの欠点】
体内への吸収率が非常にわるい
(バイオアベイラビリティが低い)
そこで登場したのがケルセチン配糖体。
ほぼ全ての動植物の生命維持に必要な
糖と結合させることで吸収率が約120倍に高まる。
糖と結合させたケルセチン配糖体に
体脂肪低減効果があることも興味深い。
体内への吸収率が非常にわるい
(バイオアベイラビリティが低い)
そこで登場したのがケルセチン配糖体。
ほぼ全ての動植物の生命維持に必要な
糖と結合させることで吸収率が約120倍に高まる。
糖と結合させたケルセチン配糖体に
体脂肪低減効果があることも興味深い。
▼ケルセチン
亜鉛イオノフォア以外の作用
▶︎新型コロナ直接阻害
EGCGの約76%程度の阻害値
▶︎線維化因子TGF-βを間接的に抑制
▶︎血流・血管内皮機能の改善
▶︎動脈硬化予防
▶︎コレステロール低減
▶︎糖尿病改善
【補足】
ケルセチン配糖体
▶︎体脂肪低減
※純成分ケルセチンでは未確認
亜鉛イオノフォア以外の作用
▶︎新型コロナ直接阻害
EGCGの約76%程度の阻害値
▶︎線維化因子TGF-βを間接的に抑制
▶︎血流・血管内皮機能の改善
▶︎動脈硬化予防
▶︎コレステロール低減
▶︎糖尿病改善
【補足】
ケルセチン配糖体
▶︎体脂肪低減
※純成分ケルセチンでは未確認
ケルセチン配糖体
体脂肪低減作用について
サントリー
グローバルイノベーションセンターの研究
ケルセチン配糖体
▶︎110mg/day
12週間の継続摂取によって
「腹部脂肪面積が有意に減少」との報告。
suntory.co.jp/sic/research/h…
配糖体で摂ることで吸収率もあがり
その他の作用増進も期待できる。
体脂肪低減作用について
サントリー
グローバルイノベーションセンターの研究
ケルセチン配糖体
▶︎110mg/day
12週間の継続摂取によって
「腹部脂肪面積が有意に減少」との報告。
suntory.co.jp/sic/research/h…
配糖体で摂ることで吸収率もあがり
その他の作用増進も期待できる。
【ここでいったん整理】
植物成分の亜鉛イオノフォアレベル
※亜鉛を細胞内へ輸送する作用度合い
▼医薬品基準値を100と設定
※基準値:クリオキノール(飲用不適)
EGCG:62
ケルセチン:31.6
ルテオリン:21.3
ルチン:7.5
レスベラトロール:1.9
亜鉛のみ(参考値):1.5
sciencedirect.com/science/articl…
植物成分の亜鉛イオノフォアレベル
※亜鉛を細胞内へ輸送する作用度合い
▼医薬品基準値を100と設定
※基準値:クリオキノール(飲用不適)
EGCG:62
ケルセチン:31.6
ルテオリン:21.3
ルチン:7.5
レスベラトロール:1.9
亜鉛のみ(参考値):1.5
sciencedirect.com/science/articl…
お気づきの方も多いと思いますが、
前掲の研究結果から判断すると
レスベラトロール:1.9
の値は非常に低く、
参考値である亜鉛のみの場合の
亜鉛の細胞膜透過性(1.5)とほぼ変わらない。
もはや、レスベラトロールを
亜鉛イオノフォア成分のひとつとして
考察する必要はないかもしれません。
前掲の研究結果から判断すると
レスベラトロール:1.9
の値は非常に低く、
参考値である亜鉛のみの場合の
亜鉛の細胞膜透過性(1.5)とほぼ変わらない。
もはや、レスベラトロールを
亜鉛イオノフォア成分のひとつとして
考察する必要はないかもしれません。
▶︎レスベラトロール
前掲の研究から判断すると
亜鉛イオノフォア作用はほぼないが、
論文では多々、イオノフォアとして扱われるため概要を解説。
赤ワインや赤ブドウの種や皮に多く含まれるポリフェノール。
植物が紫外線から身を守るための成分で人においては特に肌の健康維持に役立つとされる。
前掲の研究から判断すると
亜鉛イオノフォア作用はほぼないが、
論文では多々、イオノフォアとして扱われるため概要を解説。
赤ワインや赤ブドウの種や皮に多く含まれるポリフェノール。
植物が紫外線から身を守るための成分で人においては特に肌の健康維持に役立つとされる。
余談ですが、
植物は光合成のために
太陽光を必要とするが
強すぎる紫外線から身を守るため
レスベラトロールのような成分を生成する。
睡眠ホルモンである
メラトニンもそのひとつで
日照が強い時期の葉や種子で多く生成されることが知られている。
academic.oup.com/plphys/advance…
植物は光合成のために
太陽光を必要とするが
強すぎる紫外線から身を守るため
レスベラトロールのような成分を生成する。
睡眠ホルモンである
メラトニンもそのひとつで
日照が強い時期の葉や種子で多く生成されることが知られている。
academic.oup.com/plphys/advance…
▶︎ルチン
医薬品基準値を100とすると
亜鉛イオノフォア作用は7.5という低さ。
ただ、学術論文などでは
ルチンよりもより多く言及される
レスベラトロールの1.9よりはマシな数値。
日本人にとっては
「お蕎麦」で身近な食材ですので
次回以降、簡潔に考察しておきます。
医薬品基準値を100とすると
亜鉛イオノフォア作用は7.5という低さ。
ただ、学術論文などでは
ルチンよりもより多く言及される
レスベラトロールの1.9よりはマシな数値。
日本人にとっては
「お蕎麦」で身近な食材ですので
次回以降、簡潔に考察しておきます。
ルチンといえば蕎麦
というイメージが強いが、
これは唯一ルチンを含む穀物が蕎麦だけ
がゆえに定着したもので、
本来、ルチンはビタミンPと呼ばれ、
アスパラガスやトマト、
ミカン、タマネギ(特に皮)など
野菜や果物に豊富に含まれる成分。
当初は紫斑病(血管炎)の治療分野で発見されました。
というイメージが強いが、
これは唯一ルチンを含む穀物が蕎麦だけ
がゆえに定着したもので、
本来、ルチンはビタミンPと呼ばれ、
アスパラガスやトマト、
ミカン、タマネギ(特に皮)など
野菜や果物に豊富に含まれる成分。
当初は紫斑病(血管炎)の治療分野で発見されました。
【ルチンのホント】
天然ルチンは難水溶性です。
蕎麦で摂る場合、
多くが蕎麦湯に溶け出てしまう
というのは実はウソです。
ただ、蕎麦湯には
他の水溶性ビタミンが溶け出しているため栄養は豊富。
アスパラガスなども茹でないで
焼いて食べる方がルチンを摂れる
これも真実ではありません。
天然ルチンは難水溶性です。
蕎麦で摂る場合、
多くが蕎麦湯に溶け出てしまう
というのは実はウソです。
ただ、蕎麦湯には
他の水溶性ビタミンが溶け出しているため栄養は豊富。
アスパラガスなども茹でないで
焼いて食べる方がルチンを摂れる
これも真実ではありません。
▼ルチン
亜鉛イオノフォア以外の作用
▶︎血管の修復
▶︎歯茎の出血予防
▶︎毛細血管の強化
▶︎脳卒中予防
▶︎動脈硬化予防
▶︎高血圧の改善
これらの作用をみると、
「血液サラサラ成分」との代名詞に納得ですね。
▼補足
ビタミンCとの相性が良く、
併用することで作用値が高まるとされる。
亜鉛イオノフォア以外の作用
▶︎血管の修復
▶︎歯茎の出血予防
▶︎毛細血管の強化
▶︎脳卒中予防
▶︎動脈硬化予防
▶︎高血圧の改善
これらの作用をみると、
「血液サラサラ成分」との代名詞に納得ですね。
▼補足
ビタミンCとの相性が良く、
併用することで作用値が高まるとされる。
▶︎ルテオリン
せっかくなので前掲データから
最強「亜鉛イオノフォア」(植物成分)
EGCGの1/3程度の値があるので考察します。
▼亜鉛イオノフォア作用
EGCG:62
ルテオリン:21.3
植物が紫外線から身を守るために産生する成分。
紫菊、ピーマン、春菊、セロリ、ブロッコリーなどに多く含まれる。
せっかくなので前掲データから
最強「亜鉛イオノフォア」(植物成分)
EGCGの1/3程度の値があるので考察します。
▼亜鉛イオノフォア作用
EGCG:62
ルテオリン:21.3
植物が紫外線から身を守るために産生する成分。
紫菊、ピーマン、春菊、セロリ、ブロッコリーなどに多く含まれる。
▼ルテオリン
亜鉛イオノフォア以外の作用
▶︎抗炎症作用
炎症性サイトカインIL-6の抑制
▶︎脂肪量の低下(抗肥満)
▶︎血糖値の低下
▶︎血中脂質の改善
→抗動脈硬化作用
▶︎プリン体の合成を抑制
→尿酸値の調整(低下)
IL-6の抑制は
EGCGにも同様にみられる
サイトカインの調整作用ですね。
亜鉛イオノフォア以外の作用
▶︎抗炎症作用
炎症性サイトカインIL-6の抑制
▶︎脂肪量の低下(抗肥満)
▶︎血糖値の低下
▶︎血中脂質の改善
→抗動脈硬化作用
▶︎プリン体の合成を抑制
→尿酸値の調整(低下)
IL-6の抑制は
EGCGにも同様にみられる
サイトカインの調整作用ですね。
以上の考察ように
亜鉛イオノフォア作用をもつ
植物成分には多種多様な作用がある。
そもそも医薬品以前の病気治療は
漢方やハーブによる栄養療法だけでした。
ご自分の気になる健康懸念に応じて
植物成分を自由に組み合わせての
亜鉛イオノフォア成分の補給は
より健康的な感染予防法だといえます。
亜鉛イオノフォア作用をもつ
植物成分には多種多様な作用がある。
そもそも医薬品以前の病気治療は
漢方やハーブによる栄養療法だけでした。
ご自分の気になる健康懸念に応じて
植物成分を自由に組み合わせての
亜鉛イオノフォア成分の補給は
より健康的な感染予防法だといえます。
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh