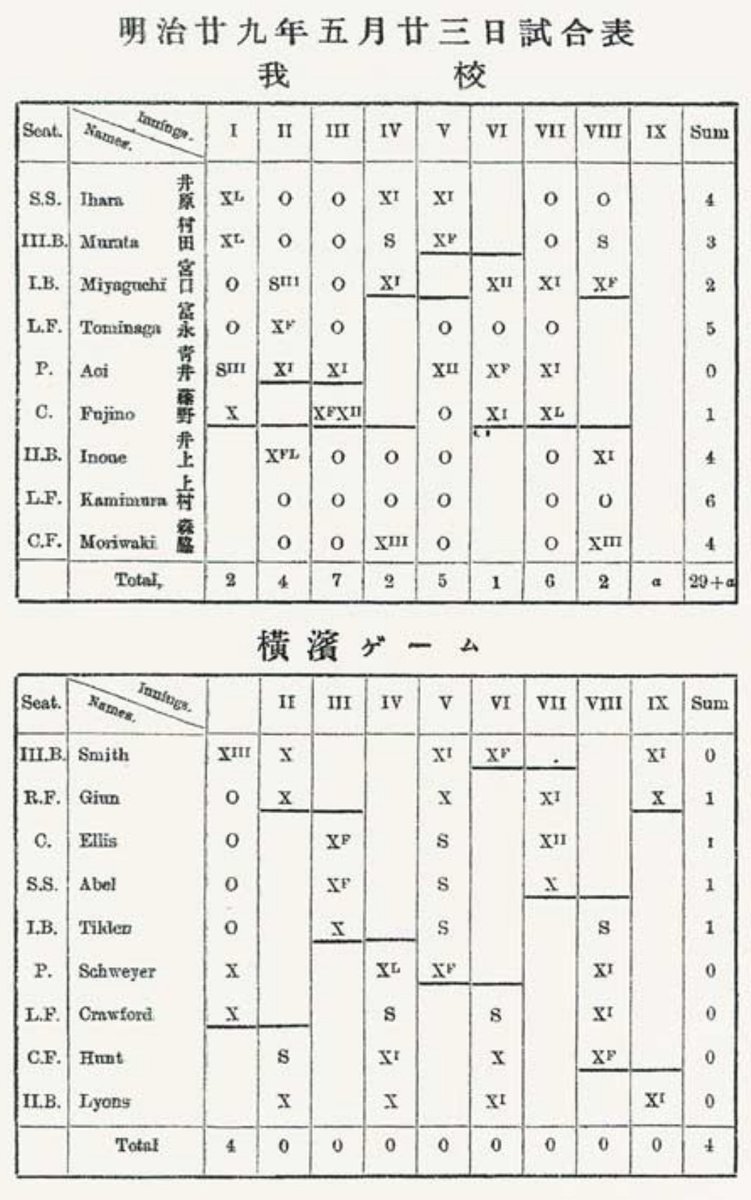青森県下北地方~北海道道南には独特の餅菓子「べこもち」がある。
もち米と粳米を混ぜて作り、模様を施した後金太郎飴のように切って蒸す料理だ。
これは江戸時代に北前船で入ってきた文化が現地で変化したもの。
なので、道南と下北では変化の仕方が異なり、下北のものはカラフルに変化していった。

もち米と粳米を混ぜて作り、模様を施した後金太郎飴のように切って蒸す料理だ。
これは江戸時代に北前船で入ってきた文化が現地で変化したもの。
なので、道南と下北では変化の仕方が異なり、下北のものはカラフルに変化していった。


青森県下北地方では戦後、時代の流れの中で少しずつ各家庭での継承が減っていた。
ところが1970年代、べこもちは役所の農林部に注目された。当時、青森県では米が余っていたからだ。
米の消費拡大と町おこしのため、伝統的柄だけでなく、工夫を凝らし様々なバリエーションのべこもちが作られるように
ところが1970年代、べこもちは役所の農林部に注目された。当時、青森県では米が余っていたからだ。
米の消費拡大と町おこしのため、伝統的柄だけでなく、工夫を凝らし様々なバリエーションのべこもちが作られるように

一方北海道道南では葉っぱ型のべこもち。
北海道ではちまきや笹餅などを作る習慣がほぼない。
そのため、その代わりに葉っぱの形をしたのではないかと言う説が濃厚だ。
北海道は広い。
元々のべこもちだけでなく、各地の文化などが混ざり合っているため、葉っぱ形以外にも様々なバリエーションがある
北海道ではちまきや笹餅などを作る習慣がほぼない。
そのため、その代わりに葉っぱの形をしたのではないかと言う説が濃厚だ。
北海道は広い。
元々のべこもちだけでなく、各地の文化などが混ざり合っているため、葉っぱ形以外にも様々なバリエーションがある

北前船で運ばれた文化なので、源流は日本海にある。
例えば佐渡には「やせうま」という類似の米菓子がある。
文化の伝言ゲームは、その地域の環境や人間の思いによって変化しながら伝わって行くものなのだ
#にいがたさくらの小話 その387
例えば佐渡には「やせうま」という類似の米菓子がある。
文化の伝言ゲームは、その地域の環境や人間の思いによって変化しながら伝わって行くものなのだ
#にいがたさくらの小話 その387

参考文献
青森県下北地方におけるべこもちの継承形態と地域的特色
u-gakugei.repo.nii.ac.jp/?action=reposi…
江差・上ノ国・松前の「ベコモチ」
do-bunkyodai.repo.nii.ac.jp/index.php?acti…
涅槃会の供え菓子 佐渡のやせごま
jstage.jst.go.jp/article/ajscs/…
餅菓子文化の伝承: 北海道における 『べこもち』
do-bunkyodai.repo.nii.ac.jp/?action=pages_…
青森県下北地方におけるべこもちの継承形態と地域的特色
u-gakugei.repo.nii.ac.jp/?action=reposi…
江差・上ノ国・松前の「ベコモチ」
do-bunkyodai.repo.nii.ac.jp/index.php?acti…
涅槃会の供え菓子 佐渡のやせごま
jstage.jst.go.jp/article/ajscs/…
餅菓子文化の伝承: 北海道における 『べこもち』
do-bunkyodai.repo.nii.ac.jp/?action=pages_…
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh

 Read on Twitter
Read on Twitter