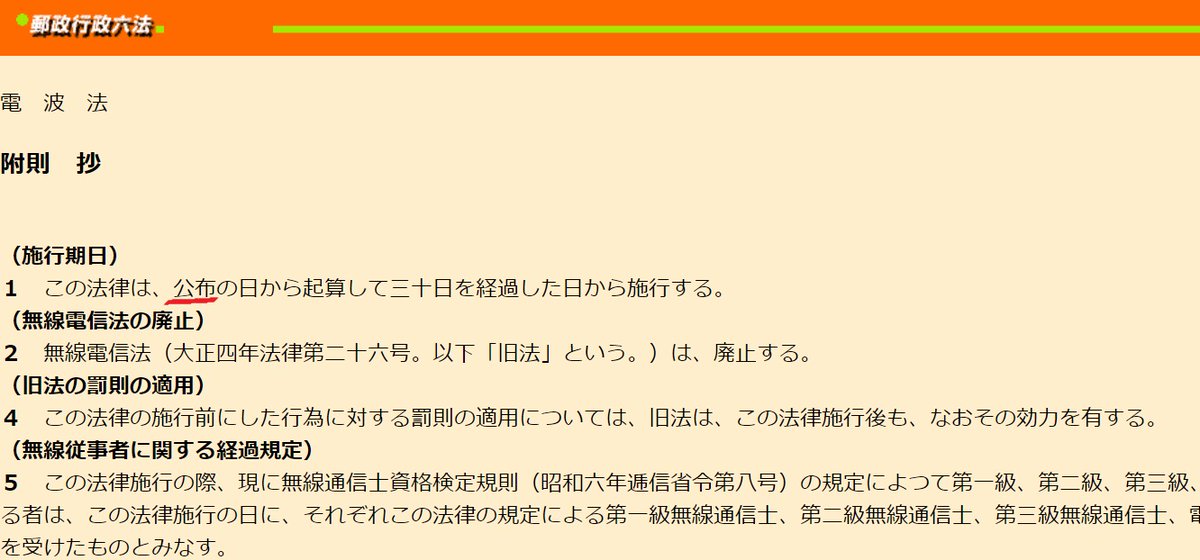弁護士。非法学部卒、元会社員。Master of Arts in Theology (Lucent University). 著作『13歳からの天皇制』(かもがわ出版)発売中!https://t.co/ZAAgvFTkR3 ブログは https://t.co/XHYUk1UFxD
How to get URL link on X (Twitter) App

https://twitter.com/YAMASHITAnoID/status/1981296257877627173→労働者(企業の勤め人)の地位が向上し利害が多様になってくると、企業の発展や経済成長を重視する労働者も増えるようになり、単に抑圧や差別に反対するだけでは労働者の心を捉えられなくなってきます
https://twitter.com/ShinHori1/status/1659830377853374464⇒
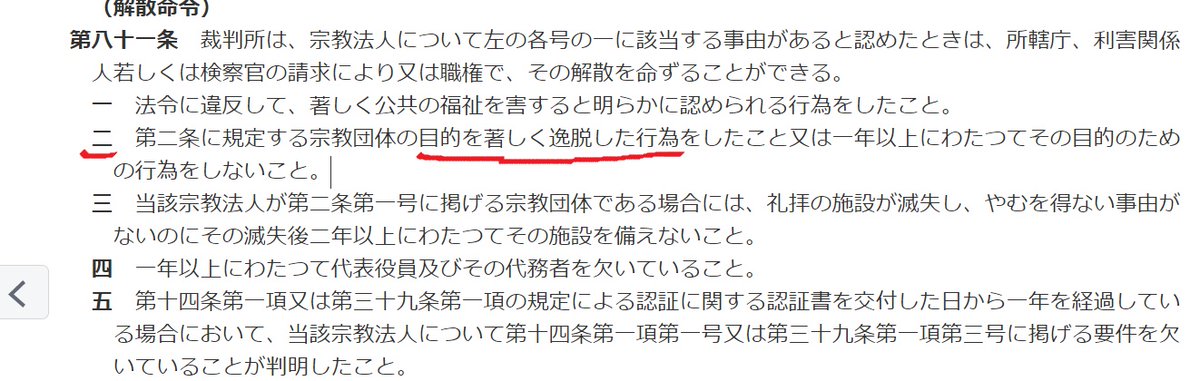
https://twitter.com/kyodo_official/status/1555383857473802240→
https://twitter.com/high_octane2960/status/1539186011879899136→

 →
→