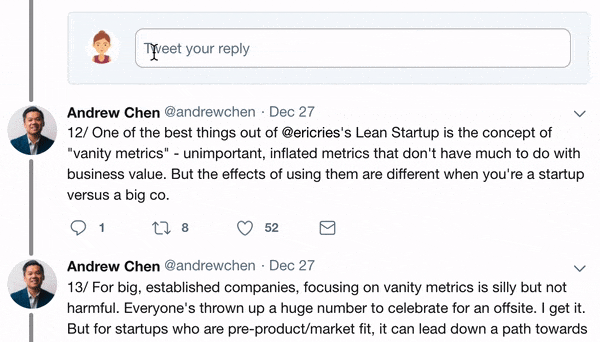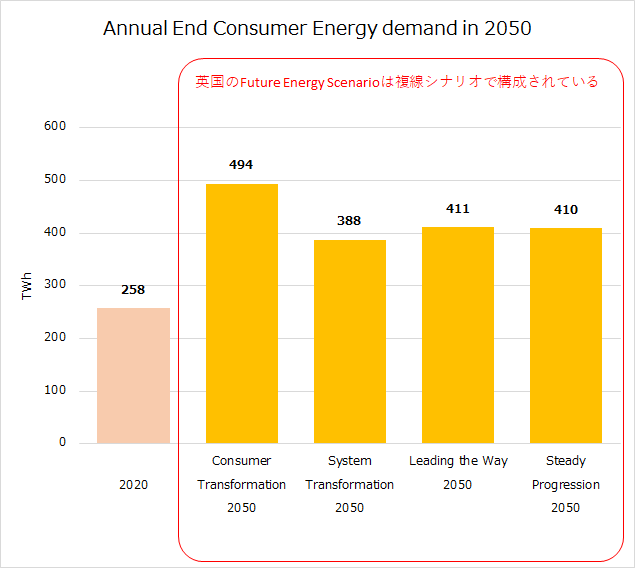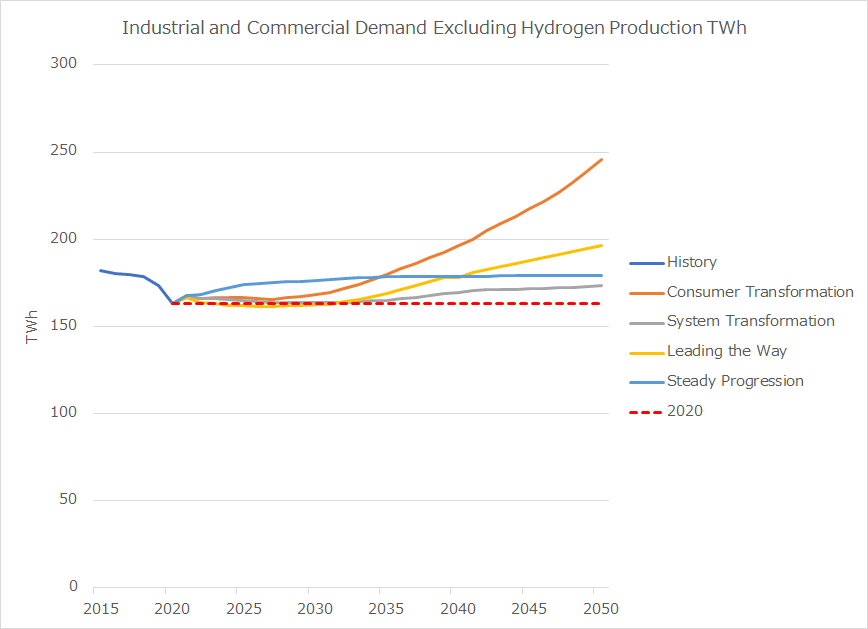※少し長くなります。
「ドイツはフランスから電気を買っているではないか。脱原発なんてとんでもない」といった返信、RTをよくいただきますが、少しそれは早計ではないかと考えます。欧州の電力市場、相互依存関係は第二次世界大戦後の、欧州協調体制の賜物であると言えるからです。私は昨年12月に
「ドイツはフランスから電気を買っているではないか。脱原発なんてとんでもない」といった返信、RTをよくいただきますが、少しそれは早計ではないかと考えます。欧州の電力市場、相互依存関係は第二次世界大戦後の、欧州協調体制の賜物であると言えるからです。私は昨年12月に
ドイツ電気事業の歴史的経緯についてツイートをしておりますが、改めて整理させていただきます。
ドイツ電気事業について考察する際に大変重要なポイントは、ドイツは1870年のドイツ帝国成立まで諸侯国連合であった点である。ドイツ帝国はプロイセン王国、バイエルン王国、
https://twitter.com/gomatsuo/status/1337704722795352065?s=20
ドイツ電気事業について考察する際に大変重要なポイントは、ドイツは1870年のドイツ帝国成立まで諸侯国連合であった点である。ドイツ帝国はプロイセン王国、バイエルン王国、
ザクセン王国、ヘッセン大公国、自由都市ハンブルクなど、4王国、6大公国、5公国、7侯国、3自由都市で成立する連邦国家であった。歴史的経緯から、ドイツでは東京やロンドンのような一極集中型の大都市が存在せず、ベルリン・ハンブルク・デュッセルドルフ・ミュンヘン・フランクフルトのように
中堅都市が分散する傾向にある。電気事業の観点では、都市部では都市火力を中心とした電気事業者として、都市以外では鉱工業需要家が自家発火力として発達し、地方自治体はこれら都市火力や自家発火力の余剰電力を購入して電灯事業を行う協同組合(今日のシュタットベルケ)を設立した。
多くの電気
多くの電気
事業者が存在することによる非効率な運営はドイツ議会でも問題意識はあり、ワイマール共和国が成立した1919年、ドイツ議会は「電気事業社会化法」(※事実上の国有化法)を成立させる。ところが、ヴェルサイユ条約によってドイツに課せられた膨大な賠償金はハイパーインフレーションを招き、国家財政
破綻の危機に瀕したワイマール共和国政府は国有化を諦めざるを得なかった。
1933年に政権を握ったナチス・ドイツは電力会社統合を目指したが、ルール工業地帯の自治体、特にノルトライン=ヴェストファーレン州から猛反発を受けた。また、国家総動員体制に向けてドイツ工業全国連盟(RDI)を政府
1933年に政権を握ったナチス・ドイツは電力会社統合を目指したが、ルール工業地帯の自治体、特にノルトライン=ヴェストファーレン州から猛反発を受けた。また、国家総動員体制に向けてドイツ工業全国連盟(RDI)を政府
傘下に収めようとしたがこれも失敗、1934年8月にクルト・シュミット経済相が解任される事態に発展する。シュミットの後任、ヒャルマル・シャハトは市場主義者であり、ナチス政権の戦時経済方針に大企業を従わせる方針を採った。1935年、エネルギー事業法が成立し、正式に電力会社国有化の方針は
放棄された。シャハト経済相による経済政策の下、ドイツの電気事業者は統合されず、多くの事業者が大戦を生き残った。1939年に電力管理法、1941年に配電統制令を施行し、日本発送電+9配電事業(北海道・東北・関東・中部・北陸・関西・中国・四国・九州)体制を完成させた日本とドイツの違いは、まず
戦前に見て取ることができる。
さて、第二次世界大戦後、ドイツは西独と東独に分割占領された。1947年アメリカは欧州の戦時復興に向けた経済援助政策「マーシャル・プラン」を開始し、欧州では経済回復に伴い電力需要が飛躍的に上昇した。しかしながら、経済回復はインフラ投資の課題を顕在化させ、
さて、第二次世界大戦後、ドイツは西独と東独に分割占領された。1947年アメリカは欧州の戦時復興に向けた経済援助政策「マーシャル・プラン」を開始し、欧州では経済回復に伴い電力需要が飛躍的に上昇した。しかしながら、経済回復はインフラ投資の課題を顕在化させ、
各国で電力不足が深刻化した。電力不足に対して、英国・フランス・イタリアは電力会社国有化により、政府保証の下で発電設備・送配電設備拡充に向けた投資を実行した(英国:1947年、フランス:1946年、イタリア:1962年)。一方、西独は電気事業を国有化せず、電気事業者の公私混合有化が進んだ。
1968年時点のRWE株式の65%は連邦政府、州政府など公共が握っていた。国有化は行わないものの、連邦政府・州政府・市町村など公的機関が電気事業者の一部株式を所有することによって支配する傾向にあった。
ドイツは電気事業国有化を行わなかったものの、投資援助法により重化学工業の民間事業者が
ドイツは電気事業国有化を行わなかったものの、投資援助法により重化学工業の民間事業者が
イニシアチブを取り、民間資本主導で電源投資を行った。当時の西独政府、電気事業者の共通認識は、電気事業の国有化は不要であり、必ずしも効果的なものではない、といったものであった。しかしながら、政策課題の重点が火力電源・送配電設備拡充から、原子力発電所建設やピーク供給力の確保、
経済運用に移るにあたって、複雑な電気事業体制の問題点が指摘されるようになる。また、この頃になると電気事業の広域運営やスケールメリットによる技術革新といった観点からの課題も指摘されるようになった。
少し時間を巻き戻すが、欧州大陸系統では、1950年頃から供給力の不足が深刻化する。
少し時間を巻き戻すが、欧州大陸系統では、1950年頃から供給力の不足が深刻化する。
1951年には600万kWの供給力が不足し、供給力の国際協調体制の確立は喫緊の課題となっていた。OEEC(欧州経済協力機構)は加盟各国に対して発電事業における共同活動を勧告、1951年5月にUCPTE(発送電協同連盟)が設立された。UCPTE発足時の加盟国はベルギー、西独、仏、伊、ルクセンブルク、蘭、
オーストリア、スイスである。UCPTEの主要業務は周波数調整・監視機能は負わず、需給計画管理・連系線運用機能のみであった。この点は日本の中央電力協議会中央給電連絡指令所と同様である。系統周波数監視機能はEGL社ラオフェンブルク給電所が、現在はSwissGridが有している。
西独はUCPTEに政府
西独はUCPTEに政府
代表や電力会社職員を派遣し、自国の経済運用実現を目指し、各国の電力融通に向けた基盤確立を目指した。
ピーク供給力として有望な電源は揚水発電所であるが、平坦なドイツの地形では揚水発電所の建設は不向きである。ドイツはオーストリア・スイス・ルクセンブルクと電力融通を行い、
ピーク供給力として有望な電源は揚水発電所であるが、平坦なドイツの地形では揚水発電所の建設は不向きである。ドイツはオーストリア・スイス・ルクセンブルクと電力融通を行い、
①ピーク供給力の確保、②夜間余剰電力の効果的処理(外国の揚水発電所を活用)、③外国の水力発電所の活用を図った。特にオーストリア・スイスには、西独が資金援助を行って揚水発電所や流込式水力発電所を建設し、ルクセンブルクはRWEが資金援助を行ってヴァイアンデン揚水発電所を建設した。
このように、西独はピーク供給力の確保や広域運営の課題を、、周辺国との電力協調体制を確立することによって解消してきたと言える。
以上、長々と説明したが、ドイツは電気事業における国際協調体制を確立することによって経済運用を実現してきたものであり、そもそも戦後ドイツの電気事業はドイツ
以上、長々と説明したが、ドイツは電気事業における国際協調体制を確立することによって経済運用を実現してきたものであり、そもそも戦後ドイツの電気事業はドイツ
単独で運用することを想定していない。これは、フランス・英国・アイルランド・オランダ・ベルギーなどの欧州諸国も同様の思想で電気事業体制が確立されていると考えられる。(了)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh