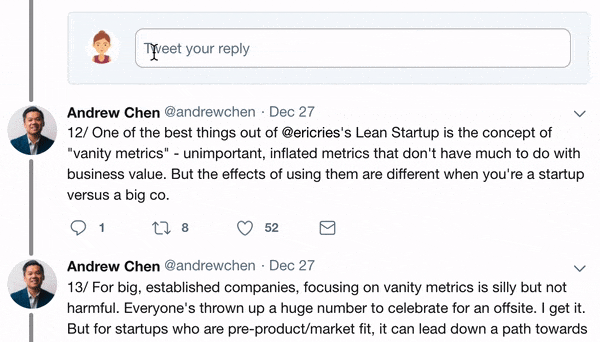シオノギの内服薬の臨床試験がひと段落し厚労省への承認申請が行われました。臨床試験がどのように進むかを概説しつつ、今回の結果について考えてみます。いろいろ議論が出ているテーマであると思いますので。最初に、二重盲検法について。これは予断を排するための手段です。 shionogi.com/jp/ja/news/202…
臨床試験では、たとえば、乳糖という白い粉末を特効薬だと医師が患者に言いつつ投与すると治療効果が見られることが古くから知られています。そこで薬効を正しく評価するために、見かけがそっくりな偽薬を用意して、投与する医師も患者もどちらを飲むかがわからないようにします。これが二重盲検法。
これに対して医師も患者も中身がわかる状態での臨床試験はオープンラベルでの試験と呼ばれます。臨床試験の段階は三つ。最初はphase 1ですが、これは安全性と薬物の体内動態を調べるのが目的。若い成人男子が対象で比較的小規模に投与してみて有害事象がないことや薬の血中濃度などを測定します。
ここで問題なければphase 2へ。phase 2は薬効確認が中心です。人数が増えるので安全性もさらに検討されます。今回の治験では少人数でのphase2aと規模拡大のphase2bに分けて行われました。最初に数十人という少人数で感触を見てから規模を拡大へ。ここで効果が確認されれば大規模なphase 3へと展開。
phase2で効果が立証されるとPOC、proof of concept が達成されたというようなことが言われます。つまり薬が理論通り効くことが示されてということです。ここから、今回の治験のデータについて考察します。治験にとって不利だったのは重症化の確率が低いオミクロン株の感染者が中心となったことです。
ファイザーの同じ作用メカニズムの内服薬では、非接種高齢者の感染者、それも強毒型のデルタ株の感染者が対象でした。本当は日本でも同様に進められれば良かったのですが、悲しいかな高齢者はほとんど接種を終えていたため治験対象者が見つからなかった可能性があります。
医薬品の効果を測定するときに測定のダイナミックレンジが大きいほど効果の測定は容易になりますが、そもそも重症化のケースが少ないオミクロン株では、症状が軽いため効果が十分観察できず、一部の症状は有意に改善されたものの、12項目という効果の総合測定では統計的な有意差なしという結果に。
これは、実はファイザーの内服薬でも同様の現象は起きていて、高齢の非接種者、そして基礎疾患を持ついわゆるハイリスクグループでは確かに効果が見られていますが、この条件から外れたグループでは同様に効果に有意差なしとなっています。したがってシオノギの内服薬の効果は現状では判断が困難。
この段階で承認するかどうかは、科学的判断というよりも、正に政治的判断となります。感染力のあるウイルスは減少していますので、治験デザインを変えれば効果がより良く観察できるかもしれません。ファイザーのように非接種、高齢、基礎疾患ありで、なおかつ強毒型ウイルスの感染者という形。
効果の立証は不十分ですが、もしも認可されたとしてもハイリスクな方に限定して使用すべきだと思います。特例承認では、残念ながら臨床試験の規模が小さく安全性が十分担保されていないからです。医薬品の承認後に大規模投与が行われた後で致命的な副作用が見つかる可能性が残されているからです。
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh