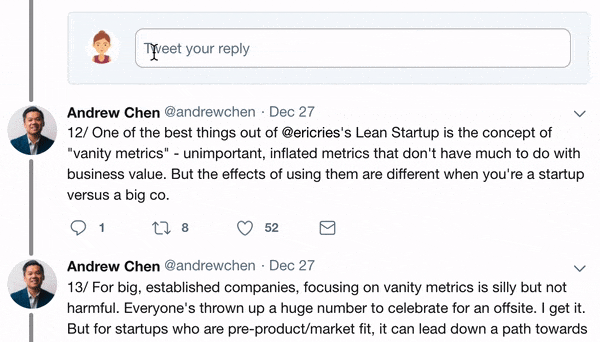#Shax_nichigei_1207 こんにちは。これから「古典演劇研究II シェイクスピア」第11回の授業を始めます。今日はジェンダーとセクシュアリティのお話をします。日芸の登録者の皆さんはスライドを準備してください。
#Shax_nichigei_1207 プロローグとして女役の話をちょっとしましょう。どうして『ロミオとジュリエット』のジュリエットは14歳にもなっていないのでしょうか?
#Shax_nichigei_1207 ここで「昔の人は早く結婚したから」というのは答えになりません。シェイクスピアの時代の平均的な初婚年齢は20代半ばくらいです。上流階級だと生活の心配がなく、政略結婚もあるので10代で結婚ということもできますが、一般人は14歳とかで結婚しません。
#Shax_nichigei_1207 おそらくこれはジュリエット役やジュリエットの母役がけっこう若かったからではないかと思われます。詳しいことは河合祥一郎『ハムレットは太っていた!』(白水社、2001)を見て頂きたいのですが、当時の女役は十代の少年がつとめました。
#Shax_nichigei_1207 ジュリエットの母も自分がジュリエットくらいの年に母親になったと言っているので、かなり若いはずです。おそらく十代半ばくらいの女役と二十歳くらいの女役がいて、そういう役者を母娘にキャストするためにこの年齢設定になった可能性があります。
#Shax_nichigei_1207 シェイクスピア劇はこういうところを考えてジェンダーについての分析をする必要があります。今回の授業ではこのプロローグの後、「第1幕 フェミニズム批評とクィア批評」、「第2幕 異性配役」という順番で話をします。
#Shax_nichigei_1207 第1幕はシェイクスピア劇のフェミニズム批評やクィア批評とはどういうものか簡単に説明します。第2幕は、これは日芸の授業で実演に役立つ内容があったほうがいいのと、あと私の研究分野のひとつでもあるので異性配役について話します。
#Shax_nichigei_1207 まず第1幕ですが、フェミニズム批評あるいはフェミニスト批評とは何かということから始めましょう。
#Shax_nichigei_1207 フェミニズム批評とは、「中立や普遍の名の下に行われてきた文学作品の解釈や価値評価は、実は男性中心主義的なものに過ぎなかった」(新田啓子「フェミニズム系批評①女として読み、女として書く」 、大橋洋一編『現代批評理論のすべて』新書館、2006、 92 – 95、p. 92)
#Shax_nichigei_1207 ということを出発点に、ジェンダーに着目した批評を行うものです。デフォルトの人間を「(白人の)男性」とし、それがあたかも人間の普遍的な価値判断であるかのような形で批評をやってきたという指摘ですね。
#Shax_nichigei_1207 一方、クィア批評の「クィア」はもともとは「変態の」「奇妙な」というような意味の侮蔑的表現です。現在ではこうした侮蔑を逆手にとって、世間的に「正常」とされるセクシュアリティにおさまらないことを「クィア」と呼称しています。
#Shax_nichigei_1207 クィア批評は基本的にセクシュアリティにおける逸脱を中心に、「何かが違う」ものをテーマに文学や芸術などを読み解く批評です。クィア=LGBTみたいに思っている人がいますが、これは違います。
#Shax_nichigei_1207 私はシェイクスピア学界のクィア批評のセミナーでひたすらお天気の話ばっかりしている発表を聞いたことがあります。
#Shax_nichigei_1207 シェイクスピア研究とフェミニズム批評の関係ですが、70年代くらいから始まりました。ジュリエット・デュシンベリの『シェイクスピアの女性像』(森祐希子訳、紀伊國屋書店、1994、原著1975)が最初のシェイクスピアに関するフェミニズム批評単著だろうと言われています。
#Shax_nichigei_1207 1977年にはL. T. Fitz [Linda Woodbridge], ‘Egyptian Queens and Male Reviewers: Sexist Attitudes in Antony and Cleopatra Criticism’, Shakespeare Quarterly 28.3 (1977), pp. 297-316. が出ています。これは『アントニーとクレパトラ』の(続)
#Shax_nichigei_1207 クレオパトラに対して男性批評家の批評にバイアスがあることを指摘した論文です。女性キャラクターの役割について貧弱な分析しかされてこなかったという議論ですね。
#Shax_nichigei_1207 それから1980年にCarolyn Ruth Swift Lenz, Gayle Greene, and Carol Thomas Neely, ed. The Woman’s Part: Feminist Criticism of Shakespeare (University of Illinois Press) が出ます。最初のシェイクスピアに関するフェミニズム批評論集だと考えられています。
#Shax_nichigei_1207 注意して欲しいのは、フェミニズム批評と呼ばれるものが始まる以前から女性の立場を考えるような批評はあったということです。シェイクスピアの女性キャラクターに注目する批評は既に17世紀からあり、マーガレット・キャヴェンディシュが『社交書簡集』で1664年にやっています。
#Shax_nichigei_1207 また、『じゃじゃ馬ならし』のような作品の性差別的側面を批判した批評家は既に古くからいます。世紀転換期にジョージ・バーナード・ショーは『じゃじゃ馬ならし』の性差別的展開を批判しています。
#Shax_nichigei_1207 批評ジャンルとして確立したのが70年代以降だということです。最初は女性キャラクターをポジティヴにとらえなおすような研究やシェイクスピアの時代の女性をとりまく環境・歴史的背景を考えて読み直すような研究が多かったです。
#Shax_nichigei_1207 その後、だんだんシェイクスピア劇における家父長制批判、男性性表象の研究、同時代の女性作家の掘り出し、シェイクスピア以外の作家の作品のフェミニズム批評、女性による受容の研究などに多角化しています。
#Shax_nichigei_1207 シェイクスピアとクィア批評については、クィア批評初期の基本書であるイヴ・K・セジウィックの『男同士の絆-イギリス文学とホモソーシャルな欲望』(上原早苗、亀澤美由紀訳、名古屋大学出版会、2001、原著1985)でシェイクスピアが扱われており、(続)
#Shax_nichigei_1207 シェイクスピア自身のセクシュアリティに関する議論もあり、クィア批評の中でシェイクスピアは初期から盛んに取り上げられる対象でした。
#Shax_nichigei_1207 シェイクスピア自身のセクシュアリティについては『ソネット集』がよく取り沙汰されます。この詩集に入っているソネットには男性について書かれたものと女性について書かれたものがあり、男性に対する賛辞が熱烈です。
#Shax_nichigei_1207 このためシェイクスピアは今で言うところのバイセクシュアルではないのかというような推測もあるのですが、正直、この詩集の内容をどれくらいシェイクスピアの個人的なことと結びつけていいのかわからないのではっきりしません。
#Shax_nichigei_1207 担当教員は詩が捧げられた相手が全員脳内彼女や脳内彼氏でもおかしくないと思っていますので(多作な詩人なら脳内恋人のひとりやふたりくらいすぐ作れるでしょう)、シェイクスピア個人の現実の性生活や恋愛はよくわからないと思っています。
#Shax_nichigei_1207 とはいえ『ソネット集』には男女両方に対する情熱が綴られているのは間違いありません。
#Shax_nichigei_1207 芝居のほうだと、『ヴェニスの商人』のアントニオや『十二夜』のアントニオは実は男性の登場人物が好きなのじゃないかというのはよくある分析で、そういう演出もたくさんあります。前者はバッサーニオ、後者はセバスチャンが好きと。
#Shax_nichigei_1207 ただしクィア批評が出てくる前から、シェイクスピア劇の同性愛的側面が指摘されることはありました。例としては前回触れたオーソン・ウェルズの『オセロー』(1951)です。イアーゴーが同性愛者だという解釈でやってますね。
#Shax_nichigei_1207 演劇研究が小説や詩の批評と大きく違うのは、演出のトレンドにダイレクトにかかわってくることです。フェミニズム批評やクィア批評も当然、実演の演出と相互に影響しあいます。
#Shax_nichigei_1207 フェミニズム批評は『じゃじゃ馬ならし』や『尺には尺を』といった作品の上演時の解釈の変化にかかわっています。『じゃじゃ馬ならし』を「夫が妻を服従させてめでたしめでたし」で演じることは今はほぼありません。何かひねりが要ります。
#Shax_nichigei_1207 『尺には尺を』はなかなかひどい話で、ヒロインであるイザベラは修道院に入ろうとしていたところを兄が逮捕されたため、嘆願に行ったところ、嘆願相手の公爵代理アンジェローからヤラせてくれれば兄を助けようと言われるという話です。
#Shax_nichigei_1207 イザベラは怒って断るんですが(当たり前だ)、この話についてイザベラもアンジェローも独善的だ、みたいな批評が昔はありました。今のような #MeToo の時代にはあり得ないと思います。
#Shax_nichigei_1207 クィア批評の影響としては、クリストファー・マーロウの『エドワード二世』(おそらく近世イングランドのメジャーな芝居では一番、男性同性愛と思われる関係が明白に描かれているもの)の上演増加などがあげられます。
#Shax_nichigei_1207 この作品の影響でシェイクスピアの『リチャード二世』(テーマにわりと共通性がある)も同性愛を織り込んだ演出がなされることが多くなりました。
#Shax_nichigei_1207 フェミニズム批評やクィア批評がなければ、人々の記憶に残るいろいろな上演は無かっただろうと思われます(第2幕でいくつか紹介しますが)。
#Shax_nichigei_1207 では第2幕、異性配役のところにいきましょう。異性配役というのは、ある役について、もともとの役柄設定と違うジェンダーの役者を配役することです。近世イングランド演劇はもともと異性配役でした。オールメールですから。
#Shax_nichigei_1207 近世イングランドのオールメール上演では、演劇的コードとして、社会通念にのっとった「男らしさ」「女らしさ」を見せる必要性がありました。「男らしさ」は大人としての成熟と結び付けられ、ひげ、背丈、剣、股袋(codpiece)などで表現されます。
#Shax_nichigei_1207 股袋というのは写真のヘンリー八世がつけている、股間をもっこりさせるアクセサリーのようなものです。時代によって何が男らしいファッションかというのはかなり違いますが、当時はこうでした。 commons.wikimedia.org/wiki/File:Holb… 

#Shax_nichigei_1207 まあ、股袋はわりと16世紀の流行なんで、シェイクスピアの最盛期の舞台ではそんなに流行ってなかっただろうと思いますが…シェイクスピア劇では7回くらいしか言及されてませんし。
#Shax_nichigei_1207 「女らしさ」としては、少年俳優を「女らしく」見せるためにどうするかということで、おそらく髪型、涙、身のこなし、声などに気を遣わねばならなかったと思われます。
#Shax_nichigei_1207 ここで触れておいたほうがいいかもしれないのがワンセックスモデルです、ワンセックスモデルというのは、超ざっくり言うと、性というのはひとつで、女性は男性の未完成な変種のようなものだという考えです。つまり男女にかなり連続性があります。
#Shax_nichigei_1207 ワンセックスモデルはトマス・ラカー『セックスの発明――性差の観念史と解剖学のアポリア』高井宏子、細谷等訳、工作舎、1998 [Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard University Press, 1992]で有名になりました。
#Shax_nichigei_1207 ただ、気をつけないといけないのは、シェイクスピアその他の劇作家が商業演劇で活躍し始める前に既にワンセックスモデルは英国で支配的なモデルではなくなり始めていたし、そもそもこれがどれくらい支配的モデルだったのかもよくわからないということです。
#Shax_nichigei_1207 今でも「性差」とは何なのかについてはいろいろごちゃごちゃした異なる考えが飛び交っていますよね?さらに一般人は別に哲学や医学の学術的なモデルに従って性差を考えているわけではないですし、近世の人が性差をどうとらえていたかというのは一枚岩で言える話ではありません。
#Shax_nichigei_1207 押さえておきたいのは、近世の性差観はたぶん現代人の性差観とはだいぶ違っていたようだということです。とくに衣服で性別を弁別することが大変重視されていました。
#Shax_nichigei_1207 フィリップ・スタッブズという人が書いた『悪習の解剖』(The Anatomie of Abuses, 1583)に、この手の話では必ず引用される有名な一節があります。「衣服は二つの性別を見分けるための弁別的なしるしとして我々がさずかったものであり、(続)
#Shax_nichigei_1207 ゆえに他の性の衣服を着る者は衣服が示す性の仲間になったことになり、自身の性の真実(his own kind)を堕落させている。それゆえ、こうした女がおとこおんな、つまり半男半女の両性具有の化物と呼ばれるのも無理からぬことである」(p. 38)
#Shax_nichigei_1207 こういう記述からは服装が性別弁別の重要なしるしであり、異性装が社会秩序に対する脅威だったことがうかがえます。シェイクスピア『十二夜』(Twelfth Night, 1600年前後)では、男装の女主人公ヴァイオラが(続)
#Shax_nichigei_1207 「かわいそうな化物(poor monster)になっちゃった私はご主君を心から愛してる」 (2.2.33)と行っています。女性が男装することは「化物」になることのように言われています。かわいそうなヴァイオラ。君は化物なんかじゃない!
#Shax_nichigei_1207 ヴァイオラはかなり活動的な女性なのですが、それでも「女は女らしい格好をすべきである」という社会規範を内面化してしまっているわけですね。
#Shax_nichigei_1207 近世イングランド演劇には男装する女性がたくさん出てきますが、喜劇には男装した女性が女に戻り、男性と結ばれて終わるという作品が多いです。これは規範無視を祝福するようでいて、異性愛中心主義の規範を追認するものでもあります。
#Shax_nichigei_1207 一方で、女性登場人物が男装することで男性にしか許されていなかった自由を享受するという楽しみの感覚も表現されます。シェイクスピア『お気に召すまま』、『十二夜』、『ヴェニスの商人』などに顕著ですね。
#Shax_nichigei_1207 このため、シェイクスピアの男装ヒロイン喜劇は演出のしかたにより、性に関する固定観念の強化にもつながれば、固定化を笑う諷刺にもつながります。ここが近世イングランド演劇の曖昧さであり、人を惹きつけているところでもあります。
#Shax_nichigei_1207 『アントニーとクレオパトラ』に"Infinite variety" 「無限の多様性」 (Antony and Cleopatra, 2.2.246)という台詞があり、これはクレオパトラの性格を表す表現ですが、よくシェイクスピア劇じたいの作風を指すものとも言われます。
#Shax_nichigei_1207 いくらでも演出で変わってしまうのがシェイクスピア劇の特色で、ジェンダーやセクシュアリティについてもそれは大いに言えるところです。
#Shax_nichigei_1207 現在における近世イングランド演劇の上演ですが、オールメール(all-male、全員男性によるもの)やオールフィメール(all-female、全員女性によるもの)でやることがあります。
#Shax_nichigei_1207 オールメールについては、同性愛への偏見が少なくなったことと、近世イングランドふうの復元上演に関心が高まっていることもあり、全員男性によるプロフェッショナルな劇団の上演は20世紀後半以降多数行われるようになっています。
#Shax_nichigei_1207 ただ、オールメールについては名目上「復元」を目指している場合、新機軸を打ち出すというよりはかなり保守的な演出になることも多いです。
#Shax_nichigei_1207 オールフィメールは一定数存在しますが、オールメールに比べると認知度が低い状態がかなり続きました。最近、 わりと盛んになってきています。
#Shax_nichigei_1207 それ以外のプロダクション(シングルセックスプロダクションではないもの)として、男女(+ノンバイナリ)の役者がいずれも出演するが、女優が男性を演じたり、男優が女性を演じたりするというものもあります。
#Shax_nichigei_1207 オールメールとしてはデクラン・ドネラン演出によるチーク・バイ・ジョウル『お気に召すまま』(1991)が記念碑的作品です。黒人の男優エイドリアン・レスターが主役のロザリンドを演じています。 cheekbyjowl.com/productions/as…
#Shax_nichigei_1207 これについてレスターが面白いことを言っています。 「ロザリンドが自分を男っぽく見せようとしている様子を演じている時の私が一番女っぽく見えると皆言ってたんですよ。私が女っぽく見せようとするのをやめると、すごく女っぽく見えたんですね」
#Shax_nichigei_1207 (Sarah Hemming, ‘Theatre / Taking Strides’, The Independent (London), 14 April 1992.)これは芝居における「わざとらしさ」はどこから出てくるのかを考えるにあたって面白い発言ですね。女っぽくしようとするとなんかわざとらしくなってしまうと。
#Shax_nichigei_1207 このオールメール『お気に召すまま』は前にも説明した人種を考慮しないキャスティングで、ロザリンドがメガネかけてたり、いろいろ面白い工夫のあるプロダクションとして有名です。レスターは舞台の大スターですが、ロザリンドは当たり役と言われています。
#Shax_nichigei_1207 日本でもオールメールは蜷川幸雄など多数試みがあります。蜷川オールメールは私の研究室にたいがいDVDがあるので、履修登録者は来れば見られます。
#Shax_nichigei_1207 オールフィメールとしては。グローブ座2003-2004のオールフィメールシリーズが有名で、『リチャード三世』(2003)、『じゃじゃ馬ならし』(2003)『から騒ぎ』(2004)が上演されました。これはもともと女役が少ないシェイクスピア劇で女優に活躍機会を与えるものでもありました。
#Shax_nichigei_1207 女役は少年俳優が演じていたということで、そんなにたくさん出来の良い十代の役者を確保できるわけでもなく、シェイクスピア劇には女性役が少ないんですね。このためシェイクスピアばかりやっていると劇場の雇用に偏りが生じます。
#Shax_nichigei_1207 それを是正するためにもオールフィメールをやると良いわけですが、一方でシェイクスピア劇のオールフィメールは「女性によるドラァグとしての女性」みたいなものも浮き彫りにします。男性を演じることを想定して書かれた女役を女優がやるので。
#Shax_nichigei_1207 フィリダ・ロイド演出のオール・フィメールシェイクスピアシリーズもよく知られています。『ジュリアス・シーザー』(2012)は刑務所の女囚が上演するという枠がありました。
#Shax_nichigei_1207 ロイドのオールフィメール『ジュリアス・シーザー』は非常に政治的で攻撃的な演出・演技で過剰な「男らしさ」の発現と、その裏にある「女らしく」見えることへの恐怖を浮き彫りにしたものでした。
#Shax_nichigei_1207 なお、この年にはロイドのオールフィメールの他、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーがオールブラックキャストでアフリカの某国が舞台の『ジュリアス・シーザー』をやったので、(続)
#Shax_nichigei_1207 「あなたが白人男性なら、今年ジュリアス・シーザーの役ができるチャンスはほとんどありませんね」(ジョージ-・ルーク)というジョークが言われたりしました。ふつうシーザーって白人男性!って感じの役ですからね。
#Shax_nichigei_1207 あと、日本では忘れてはいけない宝塚があります。宝塚もシェイクスピアネタのものをかなりやってますが、演出方針は相当違いますね。とにかく男役をカッコよくしないといけないので。
#Shax_nichigei_1207 ロイドの『ジュリアス・シーザー』のトレーラーはこれです。『ジュリアス・シーザー』は最近、日本でも森新太郎演出でオールフィメールでやってましたね。
#Shax_nichigei_1207 あと、特定の役に違う性別の役者をキャスティングするというのがあります。これはまず特定の役をスター女優にするというのがよくある例です。女優が演じるハムレットってけっこう昔からありますからね。みんなハムレットをやりたいんです。
#Shax_nichigei_1207 有名どころではフィオナ・ショウの『リチャード二世』(タイトルロール、1995、)、キャスリン・ハンターの『リア王』(タイトルロール、1997)、マキシン・ピークの『ハムレット』(タイトルロール、2014)などがあります。
#Shax_nichigei_1207 個人的な見解ですが、マキシン・ピークはかなり「私が想像するハムレット」に近かったです。これが予告です。
#Shax_nichigei_1207 それから役柄と俳優の性別の一致をあまり考慮せずキャスティングするというのもあります。一番あいそうな役者をっていうやつですね。たとえばユタシェイクスピアフェスティヴァル『ヴェニスの商人』(2018)はアントニオもシャイロックも女優でした。
#Shax_nichigei_1207 このプロダクションはシャイロック役(リサ・ウォルピ)がえらい上手で、一番後ろの席で見ていた人で「途中までシャイロックが女優だと気付かなかった」というお客さんがいました。
#Shax_nichigei_1207 日本でもカクシンハンなどは一人が複数の役を演じ、性別よりも個性重視ですね。日本のプロダクションだとカンパニーに女優のほうが多くて女性が男性役というのはたまに見かける気がします。
#Shax_nichigei_1207 それから、もとの役柄のジェンダーじたいを変更するものがあります。ほとんどは男の役を女に変更します(逆もあり)。ヘレン・ミレンが『テンペスト』(2010、映画)をやった時はプロスペロをプロスペラに変更しました。
#Shax_nichigei_1207 最近ナショナル・シアター・ライヴで上映された『十二夜』もそうですね。オリヴィアの屋敷の人はみんな女性に変更されていました。
#Shax_nichigei_1207 ただ、これは「役者の適性」に還元され、性差を問題化する意義が薄められる可能性もあります。一方で女性であるせいで…みたいな役になることもあり、いろいろですね。
#Shax_nichigei_1207 最近は雇用で不利な立場に立たされることもあるトランスジェンダーやノンバイナリの役者をちゃんと才能に即して起用しようという動きも出てきています。
#Shax_nichigei_1207 2018年エクレクティック・フル・コンタクト・シアターによる『お気に召すまま』(シカゴ)ではロザリンドの父である公爵を母に変更し、トランスジェンダーの女優ハニー・ウェストが演じ、オーランドーも女性が演じたそうです。
#Shax_nichigei_1207 劇評を見たかぎりではこれはすごく面白そうだったのですが、私は残念ながら見られていません。あと2019年アイシリスシアターによる『ハムレット』(ロンドン)もノンバイナリのジェネット・ル・ラシャがハムレット役で、それにあわせた設定でした。
#Shax_nichigei_1207 これも劇評からすると面白かったように見えるのですが、私は観劇できていません。新型コロナ以前は配信するとかいう発想がなくてアーカイブもとってない上演が多いですからね…
#Shax_nichigei_1207 最後に私が最近、注目している、日本における異性配役と「ブスネタ」問題に触れて終わります。シェイクスピアにかぎらず日本の舞台などでは男優が女装して出てくるとそれだけで「かわいくない」とされ、ブスネタで笑いをとろうとする傾向があります。
#Shax_nichigei_1207 教員が覚えているかぎりではカクシンハン『薔薇戦争』(2019)のボーナとか『泣くロミオと笑うジュリエット』(2020)のジュリエットなどについてそういうネタがあったことがありました(これは簡単に論文でも触れてます)。
#Shax_nichigei_1207 「女装男性は可愛くない」というような定型ネタはいろいろな差別につながりますし、そもそも容姿をいじるのって面白いですかね?これは日本の演劇だけではなくお笑いとか全体に通じることだと思いますが、ブスネタに安易に頼りすぎではと思います。
#Shax_nichigei_1207 プロローグとして本日のまとめを。フェミニズム批評やクィア批評をどうやって演出に生かせるかは学生の皆さんそれぞれで考えてみてほしいと思います(実演に興味がある人がほとんどでしょうから)。
#Shax_nichigei_1207 それから異性配役の上演を見て、性差について考えるには?ということですが、 役者はどうやって「男らしさ」「女らしさ」を作ろうとしているのか観察することを通して、陳腐なステレオタイプに陥っていないかなどを考えるのもいいと思います。
#Shax_nichigei_1207 異性配役により、観客が性差というものを見るにあたり、何か新しい観点やおもしろおかしい諷刺的な笑いなどを提供してくれているか?などを考えるとより舞台が楽しめると思います。演劇の醍醐味の一つは、人間の肉体について新しい見方を提供してくれることです。
#Shax_nichigei_1207 本日の授業はこれで終わります。今回はグーグルクラスルームのクイズ課題は一回、おやすみにしようと思います。それではまた来週。
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh